 台東区の神社
台東区の神社 西浅草八幡神社 | 東京都台東区
東京都台東区西浅草に鎮座する西浅草八幡神社の御朱印、由緒(歴史)、アクセスなどの紹介。旧浅草田島町(現・西浅草2丁目)の鎮守。元禄13年(1700)浄土宗江戸四ヶ寺の一つである田島山誓願寺と地域の鎮守として創建されたと伝えられる。
 台東区の神社
台東区の神社  北多摩地域の神社
北多摩地域の神社  北多摩地域の神社
北多摩地域の神社  昔の御朱印
昔の御朱印  昔の御朱印
昔の御朱印  昔の御朱印
昔の御朱印  中四国の神社
中四国の神社  昔の御朱印
昔の御朱印  北多摩地域の神社
北多摩地域の神社 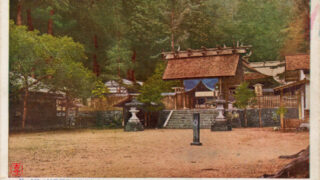 昔の御朱印
昔の御朱印